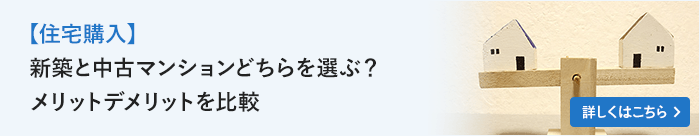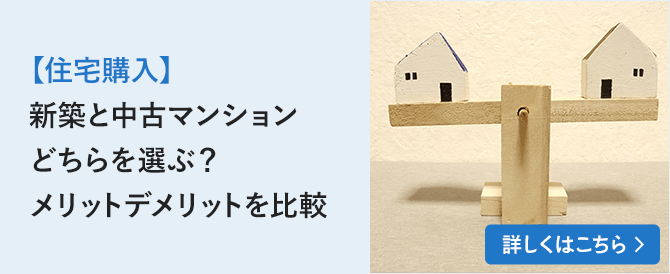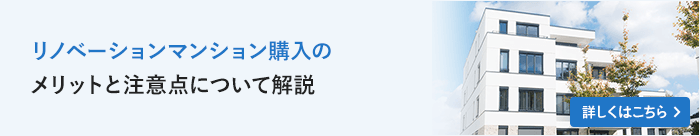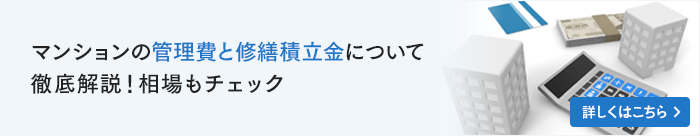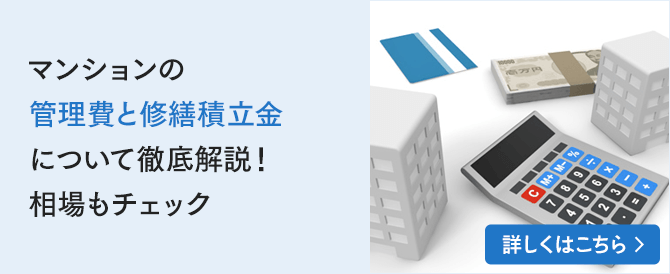中古マンションを購入したい!住宅ローンや住宅ローン控除は利用できる?

更新日:2023年11月
マイホームの購入を考える場合、最初にどのような家を購入(建築)するかを考えることになりますが、「中古マンションにしようとしている」という方もいるのではないでしょうか。
中古マンションは新築マンションよりも安いという印象を持っている人もいると思いますが、中古マンションは築年数は経過していますが、立地が良い物件も多く必ずしも安価とは言い切れません。そのため、全額を自己資金で手当てできる人は少なく、住宅ローンを利用するのが一般的です。
ただ、住宅ローンを利用した場合、「中古マンションならでは制限はあるのか?」「中古マンションでも住宅ローン控除は利用できるのか?」といった疑問を持つ方も多いと思います。
そこで、今回は中古マンション取得だからこそ知っておきたい住宅ローンの疑問点について解説します。
中古マンション購入を決意!どのくらいのお金が必要?
「新築よりも価格が割安に感じる」という理由で中古マンションを検討する人はいます。しかし、購入時に支払う金額は、広告に掲載されている金額だけではありません。中古マンションを購入する際は、物件の費用以外にも不動産会社へ支払う仲介手数料がかかる場合が多いです。
また、物件の状態次第ではリフォームの必要があるかもしれません。その場合は、リフォーム費用も上乗せとなります。これらのお金のことも考慮し全体でどの程度住居に費用がかかるか見積もりましょう。
中古マンション、リフォームなしでも住める?
中古マンション購入を検討する際に、まず確認しておきたいのは、「購入したい物件にリフォームが必要か」「必要ならばどの程度リフォームするか」です。トイレを修繕するだけなど、価格もそれほどかからないものから、全面的なリフォームが必要なものまで多岐にわたります。
リフォームする場合は、リフォーム分の見積もりが必要です。見積もりを取って、ある程度の金額が把握できたら、物件購入費用に加算して、住宅ローンで借り入れる金額を割り出してください。
中古マンションでも住宅ローンを組める
一般的に中古マンションを購入の際でも、新築マンション購入時と同様に住宅ローンを組むことができます。
リフォーム費用や諸費用まで借入できる場合がある
リフォームに必要な費用やそれに付随する諸経費は、住宅ローンに含めて借り入れることができる場合があります。
例えば、SBI新生銀行では、リフォーム資金を住宅ローンに上乗せして借りることができます。また、不動産業者に支払う仲介手数料や税金、火災保険料、修繕積立基金、管理準備金、上下水道加入負担金等も住宅ローンの融資対象になっています。
手付金の借り入れはできない
中古住宅を購入する場合、「手付金」の準備が必要になる場合があります。手付金は、契約時に必要となる資金で、購入意思の証明として機能します。住宅ローンは、住宅の引き渡し時に融資が実行されるため、手付金は自己資金で工面する必要があります。
手付金は、購入代金に充当するのが一般的です。
中古マンションの住宅ローンは築年数による制限がある
住宅ローンを利用する際には、購入物件を担保に入れるのが一般的です。中古マンションの場合は、築年数が一定期間を経過していると、担保評価が低く見積もられてしまい、融資を受けられない場合があります。
返済期間の制限
最近では住宅ローンの最長返済期間を35年等の長期に設定している金融機関を多く見受けます。ただ、一定の築年数を経過している物件の場合は、最長の借入期間が35年未満となってしまう場合があります。
借入金額の制限
築年数が経過している物件の場合は、資産価値の評価が低くなってしまい、自身の望む金額が借りられない場合があります。購入金額よりも低い金額の融資しか受けられない可能性を鑑み、売買契約の前に売主に対して価格交渉をしてみることも一案です。
住宅ローン審査に通りにくい中古マンションの特徴
中古マンションの中には審査に通りにくい物件があります。具体的には下記のような物件です。
旧耐震基準の物件
1981年6月1日より前に建てられ、新耐震基準が適用されていない物件、すなわち旧耐震基準の物件は、融資審査において評価が低くなってしまう可能性、あるいは融資自体が受けられない可能性があります。耐震性について不安要素があるからです。
中古物件を検討する際には、新耐震基準適用後に建築された物件の中から検討するのが定石です。
再建築不可の物件
接道義務を果たしていない等の理由で建て替えができない「再建築不可の物件」は要注意です。このような物件は価格が安い傾向があります。しかし、担保として取扱いができない場合が多く、住宅ローンの審査には通らない可能性が高いといえます。
借地権付きの物件
借地権付き物件は住宅ローンの対象外としている金融機関はめずらしくありません。
借地権付きの物件は、比較的価格が安い傾向がありますが、住宅ローンを利用できない可能性があることには注意が必要です。
中古マンション購入時にかかる諸費用を確認しよう
中古マンションを購入する際にかかる費用を具体的にご紹介します。
仲介手数料
購入したい中古マンションを所有者から購入する場合は、仲介している不動産会社に支払う仲介手数料が必要です。仲介手数料は、宅地建物取引業法により、400万円を超える物件であれば、以下の計算式で算出した金額以下に定められています。
- 仲介手数料=購入価格×3%+6万円+消費税
たとえば、購入代金が3,000万円の場合であれば、仲介手数料は96万円(+消費税)以下です。
なお、仲介手数料は上限しか定められていないため、値引き交渉は可能です。ただし、仲介手数料は不動産会社の利益となるため、値引きを全く受け付けていない場合も少なくありません。期待しすぎない程度に確認してみてはいかがでしょうか。
リフォーム費用
リフォーム済みの中古マンションを購入する場合は、不要です。しかし、リフォームなしで購入した場合、気になる部分を修繕するケースもあるでしょう。マンションの築年数ごとに修繕しておきたい場所と、その費用についてご紹介します。
| 築年数 | 費用の目安 (専有面積70平方メートルの場合) |
リフォーム箇所 |
|---|---|---|
| 5年 | 約10万円 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) |
| 10年 | 約105万円 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) ・温水洗浄便座の交換(約5万円) ・ユニットバスの交換(約65万円) ・洗面台の交換(約10万円) ・給湯器の交換(約15万円) |
| 20年 | 約255万円 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) ・温水洗浄便座の交換(約5万円) ・ユニットバスの交換(約65万円) ・洗面台の交換(約10万円) ・給湯器の交換(約15万円) ・キッチンの交換(約60万円) ・フローリングの張り換え(約35万円) ・クロスの交換(約45万円) ・トイレ工事(約10万円) |
| 25年~ | 約320万円 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) ・温水洗浄便座の交換(約5万円) ・ユニットバスの交換(約65万円) ・洗面台の交換(約10万円) ・給湯器の交換(約15万円) ・キッチンの交換(約60万円) ・フローリングの張り換え(約45万円) ・トイレ工事(約10万円) ・間取りを変える(約100万円) |
| 築年数 5年 | |
|---|---|
| 費用の目安 (専有面積70平方メートルの場合) |
約10万円 |
| リフォーム箇所 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) |
| 築年数 10年 | |
| 費用の目安 (専有面積70平方メートルの場合) |
約105万円 |
| リフォーム箇所 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) ・温水洗浄便座の交換(約5万円) ・ユニットバスの交換(約65万円) ・洗面台の交換(約10万円) ・給湯器の交換(約15万円) |
| 築年数 20年 | |
| 費用の目安 (専有面積70平方メートルの場合) |
約255万円 |
| リフォーム箇所 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) ・温水洗浄便座の交換(約5万円) ・ユニットバスの交換(約65万円) ・洗面台の交換(約10万円) ・給湯器の交換(約15万円) ・キッチンの交換(約60万円) ・フローリングの張り換え(約35万円) ・クロスの交換(約45万円) ・トイレ工事(約10万円) |
| 築年数 25年~ | |
| 費用の目安 (専有面積70平方メートルの場合) |
約320万円 |
| リフォーム箇所 |
・クリーニング(約7万円) ・畳の表替え(約3万円) ・温水洗浄便座の交換(約5万円) ・ユニットバスの交換(約65万円) ・洗面台の交換(約10万円) ・給湯器の交換(約15万円) ・キッチンの交換(約60万円) ・フローリングの張り換え(約45万円) ・トイレ工事(約10万円) ・間取りを変える(約100万円) |
(筆者調べ)
ご覧の通り、築年数が古くなるほどリフォームしたほうがいい箇所が増えてくるため、費用も増加傾向です。また、グレードの高い設備を選ぶと、さらに費用がかかります。リフォームの際は、どのようなグレードの設備を選ぶかも慎重に考えないといけません。
なお、以下のような場合は、売却用にリフォームしていない物件であっても、修繕費用が抑えられる可能性もあります。購入物件を決める際は、不動産会社を通じてチェックしてみてはいかがでしょうか。
- 売主がここ数年内にリフォームをしている
- 売主が部屋を丁寧に扱っている
- ペットや小さい子どもがいない(壁や床を傷つけられるおそれが少ない)
ただし、購入時はリフォームなしで問題なかったとしても、住宅の設備はいずれ古くなります。新築で購入した場合に比べて、リフォームまでの期間が短くなるため、注意してください。
ご参考に、物件の修繕サイクルを確認しておきましょう。
中古マンション購入の際の住宅ローンは新築購入時と違うの?
多くの金融機関では、住宅ローンについては中古マンションであっても、新築マンションとほぼ一緒の条件であることが多いようです。金融機関に申し込み、審査に通れば住宅ローンが利用できます。
注意したい点は、住宅ローンで借り入れる金額の中に不動産会社に支払う仲介手数料を含められるかどうかです。手元資金が少ない場合は、仲介手数料分の金額も住宅ローンに含められるかを確認してから、申し込む金融機関を決定するとよいでしょう。
中古住宅購入の仲介手数料は上述した通り、400万円を超える売買の場合、一般的に「(売買代金×3%+6万円)+消費税」が上限でかかります。物件によっては、100万円を超えるまとまった金額を準備しないといけません。
住宅ローンで仲介手数料分を借り入れない場合、自己資金で準備することも念頭に入れてください。また、手付金を先に支払うなど、支払いタイミングについても確認しておきましょう。
住宅ローン利用に必要な費用とは?
住宅ローンの利用が決まった後は、ローン利用に必要な費用も確認しましょう。金融機関によって異なりますが、主に以下の費用を支払うことになります。
| 費用名 | 内容 |
|---|---|
| 事務取扱手数料 |
・金融機関に対する費用 ・夫婦それぞれが住宅ローン契約者になる「ペアローン」の場合は、両名が支払う |
| 保証料・保証事務取扱手数料 |
・保証料を保証会社に支払うことで、契約者が住宅ローンを支払えなくなった場合、保証会社が契約者に変わり金融機関へ残債を支払ってもらえる ・ただし、契約者は保証会社に肩代わりしてもらった分を保証会社への返済は必要 |
| 団体信用生命保険料 |
・ローン支払い中、契約者が死亡や高度障害状態になった場合、保険金で借入金を相殺できる ・遺族にローン返済の義務は生じない |
| 火災保険料 |
・建物や家財が火災、風水害などで損害を受けた場合、損害の度合いに応じて保険金が支払われる ・ほとんどの金融機関で住宅ローン契約時に加入を求められる |
| 抵当権設定登記の登録免許税・司法書士報酬 |
・住宅ローンで不動産に抵当権を設定する場合は「登録免許税」が必要 ・2024年3月31日までは税率が軽減されており、一定要件を満たせば「借入金×0.1%」で算出された金額となる *本来は「借入金×0.4%」 ・手続きを司法書士に行ってもらった場合、司法書士への報酬も必要 |
| 印紙税 |
・住宅ローン契約時は金融機関と契約書を交わすため、印紙代が必要(電子契約が導入されている場合は印紙税は不要となります) ・印紙税額は、契約金額で異なる ・ペアローンのように契約が2つになる場合は、契約書ごとに印紙税が必要 |
これらの中の「事務取扱手数料」は、金融機関が自由に設定できる手数料です。また、「保証料・保証事務取扱手数料」「団体信用生命保険料」は、不要な金融機関もあります。
住宅ローン契約をする金融機関を決める場合は、主に以下のような点を確認しておきましょう。
- 諸費用が全部でいくらかかるのか
- 諸費用を自己資金から準備するか
- 諸費用は、物件購入費用と一緒に住宅ローンで借り入れるのか
なお、SBI新生銀行の住宅ローンでは、「保証料・保証事務取扱手数料」「団体信用生命保険料」は0円です。
中古マンション購入の流れ
中古マンションの購入の流れは以下のとおりです。
<中古マンション購入の流れ>
- 予算を立てる
- 情報収集&物件探し
- 物件見学
- 購入の申し込み
- 売買契約
- 住宅ローン審査&契約
- 引き渡し&融資実行
実際には、広告等を見て物件見学をした後に、その物件が買えるのかどうかを検討する、という順序の人が多いようです。そのような探し方をしていると、本来は予算オーバーの物件を無理して購入したり、チェックポイントの見落としをしてしまうケースがあります。
予算を立て、広く情報収集をしてから段々と希望の物件を絞り込んでいくのが正攻法といえます。
中古マンションの住宅ローン審査ってなにを見られる?期間は?
中古物件を購入する際には、「築年数が古い、不便で土地価格が下落している地域」などの要素が見られる場合、利便性の高い人気の地域にある新築物件よりも担保評価が低く見られてしまう可能性はあります。
ただ、担保評価は審査項目の一部です。
国土交通省が発行している「令和4年度民間住宅ローンの実態に関する調査」を見ると、金融機関が住宅ローンの融資の際に考慮している主な事項は以下のとおりです。
<融資を行う際に考慮する項目(上から5位までを抜粋)>
- 完済時年齢
- 健康状態
- 借入時年齢
- 担保評価
- 勤続年数
(出典)国土交通省 住宅局 令和4年度 令和4年度民間住宅ローンの実態に関する調査
物件に関する事項、すなわち「担保評価」は4番目に記載されています。それ以外の年齢や健康状態、勤続年数は「借り主」に付随する事項です。完済時年齢が規定を超えてしまう場合は、どれほど物件の価値があっても希望の返済期間を選択することはできません。
中古物件を購入する方は、担保価値が気になるかもしれませんが、それ以外の項目の影響度が高いことについても念頭に置く必要があります。
中古マンションの住宅ローン控除について
中古物件でも住宅ローン控除は利用できます。本記事執筆時点(2023年10月)の中古物件の住宅ローン控除の主な内容は以下のとおりです。
<中古物件の住宅ローン控除の内容>
| 控除対象借入残高限度額 カッコ内は税額控除の限度額 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 認定住宅 | 3,000万円(210万円) | |||
| ZEH水準省エネ住宅 | ||||
| 省エネ基準適合住宅 | ||||
| 一般の住宅 | 2,000万円(140万円) | |||
| 控除率 | 年末の借入残高×0.7% | |||
| 控除期間 | 10年 | |||
| 所得要件 | 合計所得金額2,000万円以下 | |||
(出典)国税庁タックスアンサー「1211-3」を基に筆者作成
現行の住宅ローン控除は、住宅の性能によって税額控除の限度額が異なります。物件購入時には、売主または不動産仲介会社から、物件の性能評価の詳細を入手しておくようにしましょう。
住宅ローン控除の制度について詳しくは、国税庁ホームページなどでご確認ください。
中古マンションについてリフォームも大事だけど大規模修繕の実施状況や修繕積立金の状況についても気になる方は以下のコラムをご参考ください。

えんどう こうじ
- CFP(R)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。
当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
新着記事
閲覧が多い記事
おすすめ記事
マイページへ登録済みの方は
こちら
住宅ローン関連コンテンツ
パワースマート住宅ローンについて
- 借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。
- 借入期間は、変動金利(半年型)をご選択された方で新規に住宅購入・建設資金のお借り入れの場合は5年以上50年以内(1年単位)※、それ以外のお借り入れについては5年以上35年以内(1年単位)です。※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。
- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。
- お借り入れに際しては当行所定の審査がございます。審査結果によっては、借入利率等の借入条件がご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。
- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税※、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。※電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。
- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。
- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。
- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。
- 1つのお取引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます(ただし、同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを実施している場合もございます)。
[2025年11月17日現在]