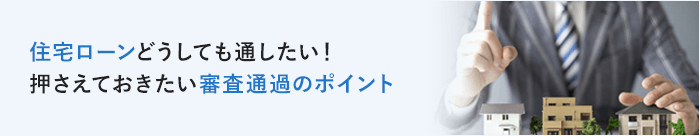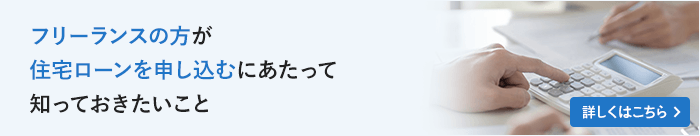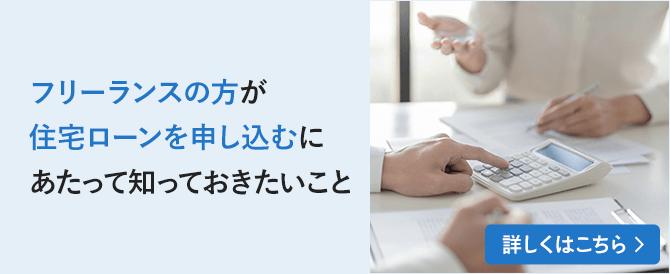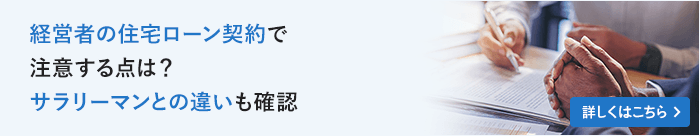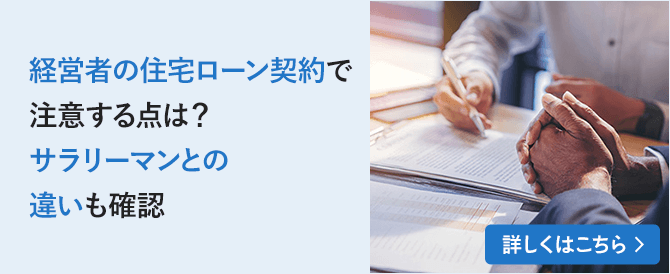自営業・個人事業主の方が住宅ローンの申し込みをするポイントは?

更新日:2025年3月
「自分は自営業だけど住宅ローンは組めるの?」という不安をもつ人は多いと思います。会社員と比較して収入の安定性が不安視されやすい自営業の方ですが、もちろん住宅ローンを組めないというわけではありません。実際、これまで多くの自営業の方が問題なく住宅ローンを借りています。
この記事では、自営業の方が住宅ローンを申し込む際に押さえておきたいポイントについて解説します。
自営業以外の方はこちらをご覧ください。
なお、この文章中における「自営業」とは、法人化していない個人事業主を指します。
自営業の方の住宅ローンお申し込み条件とは
会社員・公務員の方と比べて、自営業の方は、申込時の条件が以下のように異なる場合があります。例えば、SBI新生銀行の住宅ローンの商品説明書を見ると、申し込み時の条件として下記のようなことが書かれています。
- 前年度税込年収が300万円以上の正社員または契約社員であること。
- 自営業の方については業歴2年以上、かつ2年平均300万円以上の所得(経費控除後の金額)を有すること。
(出典)SBI新生銀行 <パワースマート住宅ローン> 商品説明書より引用(2025年2月現在)
上記のようにSBI新生銀行の住宅ローンを自営業の方が利用するには、業歴2年以上が必要なことがわかります。
他の金融機関では業歴を3年以上とするケースが多くあります。実際、自営業をスタートしてからビジネスが安定するまで、一定の期間がかかるため、2~3年の業歴を必要としていることについては、特段、不自然ではないと思います。
自営業の方が住宅ローン審査を受ける時の年収条件と計算方法
前項の引用箇所を見てわかるとおり、正社員または契約社員は「税込年収」が年収条件になっていますが、自営業の方については、「所得」が基準になっています。一般的に所得は、収入から必要経費を引いた後の金額です。下記に例を示します。
| 事業収入(=年収もしくは年商) | 1,000万円 |
|---|---|
|
必要経費 (店舗や工場の家賃、仕入代金、光熱費等事業を行う上で必要な経費) |
700万円 |
| 事業所得 | 300万円 |
年収(年商)が1,000万円で、必要経費が700万円であれば、300万円の事業所得が確保されているということです。
金融機関側は「年収1,000万円」を見るのではなく、あくまでも所得である「300万円」を見て審査します。自営業の方は普段は「収入」すなわち「年商」を気にしていると思いますが、住宅ローン審査においては所得(=利益)が重視されるものと理解しておくとよいでしょう。
自営業の方が住宅ローン審査に通りにくい理由
自営業の方は、一般的に住宅ローン審査に通りにくい、といわれています。会社員であれば、勤続年数や収入を基に客観的に審査ができます。例えば大企業に勤続して10年たつ中堅社員の収入が急減する可能性は低いと考えるのが一般的です。
一方、自営業の方には企業の後ろ盾がありません。有力な取引先との関係悪化や、景気後退等の理由で事業の継続が難しくなった場合、急に収入が断たれてしまう可能性があります。
事業を営んでいると、収入が途絶えても固定費の支出が伴うものです。この支出は生活費とは別にかかります。
また、事業のための負債も審査においてはマイナス要因になります。金融機関は住宅ローン以外の負債も含めて顧客にとって借入希望金額が過大でないかどうかを審査しています。事業用の負債が多い人ほど「借り入れが過大である」と判定されてしまう可能性が高いということです。
自営業者・個人事業主は住宅ローン審査に通らないって本当?
自営業者・個人事業主でも住宅ローン審査に通る可能性は十分にあります。
ただし、自営業者の審査の場合は、収入ではなく所得が重視されるのが一般的です。税金対策を目的に費用計上を積極的に行なっている人は、所得が少なくなってしまうため、審査に通る可能性が低くなります。
また、フリーランス等の個人事業主になったばかりの方は、銀行が審査の基準とする2~3年分の所得がないため、審査を受けられないこともあります。
働き方は大きく変えずに、契約形態を雇用契約からフリーランスとしての業務委託契約に変える人もいますが、住宅購入を検討している方は、フリーランスへの転向は慎重に検討した方が良いといえます。住宅ローン審査においては、現時点の職業や収入の安定性が重視されるからです。
なお、中小企業庁が発行している中小企業白書(2024年版)によると、2023年度に休廃業・解散した企業の件数は、(株)東京商工リサーチ「『休廃業・解散企業』動向調査」で2022年49,625件が2023年49,788件に増加、帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散』動向調査」で2022年53,426件が59,105件が増加と記されており、相当数の休廃業が見られることから事業の継続は簡単ではないことが示されています。
自営業の方が住宅ローン審査を通るためのポイント
自営業の方が住宅ローン審査に通るためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。
<自営業の方が住宅ローン審査を通るためのポイント>
- 一定の所得を確保した事業年度を経る
- 借入希望金額を抑えめにする
- 担保価値の高い物件を選ぶ
前述のとおり、自営業の方の審査は所得に基づいておこなわれます。仮に収入が一定であるなら、経費削減を意識することが重要だということです。さらなる収益源創出が重要である点はいうまでもありません。
また、「頭金を用意する」「安価な物件を探す」といった形で、借入希望金額を抑えるのも審査に通りやすくする1つの方法です。
物件の担保価値も重要です。金融機関は、債務者が返済不能になった際に、担保物件を売却することによって資金回収に動くからです。
自営業の方が審査に落ちる典型的パターン
ここで、自営業の方が審査に落ちるパターンについてご紹介します。ただ、金融機関は審査に落ちた理由は教えてくれないため、下記はあくまでも落ちてしまった理由として推測されるものをあげています。
<審査に落ちてしまうパターン>
- 所得に対する返済負担率が高い
- 物件の担保価値が低い
- 負債が多い
- 滞納履歴がある
所得に対する返済負担率が高い
返済負担率とは、年収に占める年間の返済額の割合のことです。先述のとおり、自営業の方は収入ではなく、所得を基準に審査を行います。返済負担率も所得で見るということです。収入が高くても所得が低い人は、審査に落ちてしまう可能性が高いといえます。
物件の担保価値が低い
物件の担保価値が低いと審査に落とされてしまうことがあります。自営業の方は収入の安定性を不安視されやすいため、担保価値に疑義があると審査に落ちてしまう可能性は高くなるといえます。
負債が多い
事業用の設備などで高額な負債を抱えていると、金融機関側が「負債が多すぎる」と判断し、審査に落ちてしまうことがあります。
滞納履歴がある
クレジットカードなどの返済の滞納があると、信用情報機関に氏名が掲載され、ローン全般の審査に通りにくくなります。自営業の方は、会社員のように決まった給与振り込みがあるわけではないため、資金繰りのチェックは重要になります。
自営業の住宅ローン申し込みで提出する書類とは?
次に、自営業の方が住宅ローン申込時に提出する必要書類を見てみましょう。提出書類は、以下のようになっています。
- 以下は一例です。金融機関や住宅購入、借り換えなど目的によって異なる場合もあります。
| 本人確認のための書類 | (以下の中からいずれか2点)
|
|---|---|
| 収入面の審査のための書類 |
|
| 返済中の借り入れに関する書類 (既存の借り入れがない場合は不要) |
|
| 物件の審査に関する書類 |
|
本人確認に関する書類や、物件の審査に関する書類は、自営業でなくても必要です。しかし、特に会社員の場合と異なるのは、収入面の審査のための書類です。
会社員の場合、個別に所得税の確定申告をしていなければ住民税課税決定通知書などで審査できるケースが多い傾向です。しかし、自営業の方の場合、所得税の確定申告書の控えで直近の所得を確認する必要があります。
自営業など、フリーランスの人が住宅ローンを申し込む際に知っておきたいことについてはこちらもご覧ください。申込時の注意点、審査のポイントについて解説しています。
自営業の方の住宅ローン控除は注意が必要
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に0.7%を乗じた金額が所得税から還付される税額控除の制度(2022年度税制改正後)です。自営業の方が住宅ローン控除を利用する際には、注意が必要です。
自宅を事務所にする場合は要注意!
住宅ローンは、あくまで居住する自宅を購入・建築するときのためのローンとなるため、主に仕事で使う場所の購入のためには使えません。
自宅兼事務所を対象にする場合は、居住部分の床面積は50%以上が必須です。
工場や店舗などのように明らかに事業用と目される箇所が間取り上にある場合は、住宅を購入・建築計画をする時点で税務署に確認しましょう。
- 住宅ローン減税の制度について詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
自営業の方の住宅ローン控除手続き
会社員・公務員の人が住宅ローン控除手続きをする場合は、住宅ローンを借り入れした1年目に所得税の確定申告を行い、2年目以降は勤務先の年末調整で手続き可能です。
しかし自営業の方が住宅ローン控除を行う場合は、毎年確定申告を行わなければなりません。所得の申告と同時に手続きすることを忘れないようにしましょう。
経営者の住宅ローンの注意点
SBI新生銀行の住宅ローンの場合、法人の経営者が住宅ローンを申し込む場合も、自営業の方と同様に「業歴2年以上で2年平均300万円以上の所得」が必要です。
法人の経営者であっても、申込時に提出する書類は自営業と同じですが、以下の書類を追加して提出する必要があります。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人の決算報告書 | 勤務先 (経営している法人) |
|
| 法人税の納税証明書その1、その2 | 税務署 |
|
- SBI新生銀行の例でご紹介しています。詳しくは住宅ローンを申し込む金融機関で確認してください。
会社経営者の人も自営業の方の人と同様に、返済能力があるかを厳しくチェックされます。法人が連続して黒字状態となっているなど、事業が安定した状態であれば審査に通る可能性は高くなります。
経営者の住宅ローン契約については、こちらもご覧ください。申込時の必要書類から審査、住宅ローン控除について詳しく解説しています。
審査に必要な書類と収入資料の見方
自営業の方が住宅ローンに申し込む際には、以下の書類が必要になります。ここでは、SBI新生銀行の例で、新築戸建を新規借り入れで購入するケースで示します。
【本人確認書類】
下記いずれか2点
- 運転免許証、個人番号カード、住民票の写し、在留カードまたは特別永住者証明書
【収入審査書類】
- 直近2年分の所得税の確定申告書
- 直近2年分の所得税の納税証明書
【不動産審査書類】
- 土地建物の売買契約書
- 重要事項説明書
- 建築確認申請書
- 確認済証
所得税の確定申告書の見方
先述のとおり、自営業者は確定申告において、収入金額ではなく所得金額で審査される傾向です。所得金額は収入審査書類のうち、所得税の確定申告書に記載されています。
所得税の確定申告書は左の欄の上段から、収入金額等、所得金額等の順に記載をします。自営業者は収入金額の下に書かれている所得金額等が審査対象になっているということです。この欄の金額が300万円に満たない場合は、少なくともSBI新生銀行においては借り入れ条件をクリアしていないということです。
自営業者が住宅ローンを組む場合の注意点
住宅ローンにおいて審査通過はゴールではなくスタートです。住宅ローンは借りてから長期に渡る返済が続くからです。自営業の方は会社員と異なり、収入の急変が起きる場合があります。この項では、自営業の方が住宅ローンを組む前に確認をしておいていただきたいことを記載します。
【自営業者が住宅ローンを組む前に確認をしておくべきこと】
- 収入の急変に対する備えは十分か
- 余裕を持った返済計画になっているか
- 団体信用生命保険(団信)の保障内容は確認したか
- 流動性や資産価値が高い物件か
収入急変に対する備えについて
固定的な給与が得られる会社員や公務員と比較して、自営業の方の収入はリスクに晒されていると言わざるをえません。例えば、2020年に新型コロナウイルスによる経済混乱が起きた際には、多くの飲食店が売上減少に苦しみました。このような収入減少の事態が起きた際にも、2〜3年は返済が続けられるための緊急用資金を準備しておきましょう。
返済計画について
毎月の収入で返済できるギリギリの金額を借りるのではなく、多少の収入減少が生じても耐えられる程度の借入金額に抑えておくと安心です。また、繰上返済をする場合は、返済額軽減型を選択すると、毎月の返済に余裕が生じやすくなります。
団信の保障内容について
会社員と異なり自営業の方には有給休暇や、病気等で働けなくなった際に健康保険組合から支給される傷病手当金がありません。風邪くらいであれば気にしすぎることはありませんが、がんなどの治療が数ヵ月間に渡るような病気には備えが必要です。ガン保険や所得保障保険で備える手段はありますが、これらの保険は住宅ローンの残債を完済するほどの保険金額に設定されていないものが多いです。
住宅ローンに付随されている団信は、死亡・高度障害時に保険金によって残債を完済できる保険ですが、疾病の保障は付いていないのが一般的です。
SBI新生銀行では死亡・高度障害だけでなく、がんになった際にも残債が保険金によって完済されるガン団信を取り扱っています。がんは日本人の2人に1人は罹患すると言われており、現役世代の方々でも年齢とともに罹患者が増加してくる病気です。全ての病気に保障をかけることは難しい中、がんに特化した保険は合理性が高いといえます。
SBI新生銀行では、ガン団信の上乗せ金利が年0.1%に設定されています。魅力的な保障内容ではありますが、毎月の支払いが増加する点には留意し判断する必要があります。
流動性や資産価値について
もし、事業が思わしくなく、返済が苦しくなってきた際には、住宅ローンには「物件を売却して完済する」という手段があります。このような手立てが打てるのは、買い手がすぐに見つかるような流動性が高く資産価値が高い物件です。住宅ローン返済の滞納が続くと、金融機関が物件を競売にかけ、安値で売られてしまうことがあります。流動性が高く資産価値がある物件であれば、売却で得た資金で住宅ローンを完済し、生活を立て直す機会を得やすくなります。「なかなか物件が売れないうちに競売に至ってしまった」という事態を防ぐために、流動性や資産価値は物件選びの重要な要素だといえます。
住宅ローンの審査に不安があるなら、一度金融機関に相談しよう!
「住宅ローンが組めるか不安」「自分の借入希望金額が借りられるのか知りたい」という自営業の方も多いと思います。
その場合は、遠慮なく金融機関の担当者に相談してみましょう。
最近は、SBI新生銀行のようにお電話で相談ができる金融機関もあります。
住宅ローンは、この先何十年も付き合っていくローン商品です。事前に不安を解消し、納得できる状態で借りるようにしましょう。

えんどう こうじ
- CFP(R)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。
当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
新着記事
閲覧が多い記事
おすすめ記事
マイページへ登録済みの方は
こちら
住宅ローン関連コンテンツ
パワースマート住宅ローンについて
- 借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。
- 借入期間は、変動金利(半年型)をご選択された方で新規に住宅購入・建設資金のお借り入れの場合は5年以上50年以内(1年単位)※、それ以外のお借り入れについては5年以上35年以内(1年単位)です。※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。
- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。
- お借り入れに際しては当行所定の審査がございます。審査結果によっては、借入利率等の借入条件がご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。
- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税※、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。※電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。
- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。
- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。
- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。
- 1つのお取引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます(ただし、同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを実施している場合もございます)。
[2025年11月17日現在]